- HOME
- 社史編纂・記念誌制作:社史制作の5原則
最終更新日:2025年5月27日
社史編纂・記念誌制作 〜社史が伝える風雪の記録 記念誌が刻む不滅の記憶〜
社史は必ず「面白いもの」にできます。
「ハイコストの社史作り」よサヨウナラ。
お手頃で立派なMy社史が作れます。
社史制作の5原則 — 押さえておきたい社史制作五つの「肝」
はじめに——「社史って何?」 から考える—「書かれる」ことの意味
近年、企業の周年記念事業として社史の刊行が広く行なわれるようになりました。そうした節目に制作した社史を贈呈しあうことが、企業間交流の新たなトレンドにもなってきているようです。
しかし、社史とは何か、社史づくりの意義は何かと考えてみると、これは分かったような分からないような問題です。社史をつくったからといって会社にとってのメリットがすぐに目に見えて現れるわけでもありませんし、社史をつくらないからといって日々の企業活動に何か不都合が生じるというものでもありません。しかし、よく頂くご質問、「社史を作ることのメリットは何ですか」へのお答えをまず冒頭に掲げておきますと。それは「自分の会社を強くする」ために役立つ――ということです。その理由と、そうした社史を作るために必要な考え方のポイントをこのページでは5つに分け、解説しています。
「社史」という言葉は、ある社(団体)の関係者が「私たちの記録」という私的で固有名詞的な意味合いで『○○社 社史』と題する本を発行したというようなことが初期の使われ方だったのですが、今ではすっかり普通名詞化しています。そこまで社史づくりが一般化してきているのは、なぜなのでしょうか。
まず、その前に、歴史と人間存在というものの関係を考えてみましょう。「歴史上の人物」という言葉がありますが、考えてみれば人は誰でも歴史の中に生きるのですから、そういう意味ではみんな「歴史上の人物」であるはずです。しかし、「歴史」という言葉は単に時間的な過去を意味する場合もあれば「過去の記録」を意味する場合もあります。つまり人は誰でも過去の時間内に存在したという意味では例外なく「歴史上の人物」なのですが、その人について何かが文字で書かれない以上は歴史上に存在しないことにもなり得てしまうのです。
過去の時間上には無数の人々が存在していたに違いないのですが、その人について何の記録も書かれていないとき、何がその人が存在したことを示すのでしょうか。人はどうやってその人が存在したことを知り得るのでしょうか。つまり、どうやってその人は歴史の中に存在できるのでしょうか。
これこそが、「文字」というものの意味の始まりに直結しています。「書かれないものは存在できない」ということを「文字」を持った人間は考えるに至ったわけです。ですから、「社史をなぜ書くか」の答は「歴史の中に、人の記憶の中にちゃんと存在したいから」ということになります。
弊社が社史づくりをお手伝いする会社の経営者の方に「なぜ社史をおつくりになるのですか」とお尋ねしますと、圧倒的に多いお答えは「残したいから」というものです。次に多いのは「伝えたいから」です。その2つのお答えの目的語は「会社の歴史を」ということになると思いますが、それはたいていの場合、それほど明瞭には語られません。
そこには「会社の歴史」というだけでない、もっと深くて具体的なもの、もっと掘り下げた人間的な思いのようなものも歴史として残したいのだ、という気持が窺えます。
つまり、「残したい」「伝えたい」のは「会社の歴史」ではあっても「単なる歴史」ではなく、その「会社の存在」であり、「会社を存在させ活動した人々の存在」であり、そして「そこにあった人々の一度限りの生命の存在」なのです。さらに端的に言い切ってしまいましょう。社史とは会社とともに過ごした人々の二度とない人生がそこにあったことの確かな「生きた証(あかし)」であり、誰にとっても貴重な命の「存在証明の書」なのです。一番基本的な前提としてのこうしたことを踏まえて、社史とは何か?、良い社史をつくるための方向性の取り方は?、ということを整理してみました。
弊社が考える「社史」の定義——社史の本質(芯)は「経営史」 (牧歌舎方式1—経営史(経営ドキュメント)として書く)
社史とは何か
そもそも「社史」とは何でしょうか。
社史を普通に「会社の歴史」とだけ考えてつくりますと、内容が非常に漫然とした統一感のない印象の作品になるものです。そのため、制作途中から「このやり方でいいのだろうか」と悩んだり、完成後に「もっと充実感のあるものにするやり方があったのでは」と不完全燃焼のような思いを抱く結果になってしまったりするものです。
もともと、「社史とは何か」がよく分からないままに制作に取りかかっているのですから、よく分からないようなものが出来上がってしまうわけで、それを心配する制作ご担当者様から、よく聞かれます。
「社史って、いったい何なんですか?」
「社史って、何をするものなんですか?」
いらだち混じりの、悲鳴のようなご質問です。そこでお答えします。
「社史は、会社の経営史です」
すると、それを聞いたご担当者様はハッとしたような目になり、急いでそれをメモされるのです。今まで何度、その光景を見たかしれません。
「会社の歴史」を略して「社史」——というだけでは、何をどう作っていいのやら分からない。年表だけではいけないのか、あるいは、年表を文章にすれば事足りるのではないかと思うが、何か違うような気がする、いったい何なんだ、という思いでおられたのでしょう。それが、「経営史」と聞くと、いっぺんで考えが絞られ、まとまるようです。
「会社の歴史」では何だか分からない、何をすればいいかも分からないものだったのが、「経営史」と聞くと「人の行いの歴史」ということになりますから、それを調べてまとめればいいのだと手の打ち方がつかめるのだと思います。そして、「経営史」が社史の本質であるという「概念」をはっきり掴んで作業を進めていくと、それが「本質」であるという知的理解から、それこそ「芯」であるという精神的理解にまで高まっていくものです。
このことをさらに考えてみますと、社史は「その会社自身が作るもの」ですから、ただの「事実の記録」でなく、「会社が主語になった会社の自分史」としてまとめられなければ、読んでも「ピンと来ない」ものになってしまうということとつながります。「会社の自分史」にしようとは思っていても、では会社にとっての「自分」とは何なのかがはっきりしなければ、結局は年表をただ文章化しただけのようなものになってしまうのです。
そこで、「会社の自分史」というときの「自分」とは何かということを突き詰めて考えた結果、牧歌舎はそれを「経営者」(経営陣)とすることで自分史として必要な脈絡がつながることを確認し、「社史の本質(芯)は経営史である」と皆さんに説明するようになりました。つまり、社史は単に無限定の「会社の歴史」でなく、創業者がどのような経営目的と経営理念をもって創業し、どのように会社を維持・発展させようとし、時々の経営課題にどのような経営判断を行ってどのような経営戦略を立て、そして結果としての経営状況がどのように推移したかを記した「経営史」として書かれて初めて「社史」になる、という考え方です。
社史が照らし出す「経営の航跡」

つまり会社を一隻の船に例えれば、その「かじ取り」の跡、すなわち「経営の航跡」を照らし出すのが社史なのですが、非常に多くの場合、指摘されるまでそれが理解されていないのが実情です。会社というものが具体的な人間とは異なる次元の抽象観念として捉えられてしまっているので「会社の自分史」など作り方の見当も付かないということでしょう。
その、人間とは別存在の「会社の歴史」を「経営史=人間の歴史」に置き換えることで、抽象から具象への変換が可能になり、生きた人間の言葉で語ることができるようになるというわけです。このようにして、「会社の歴史」は「経営史」として書かれて初めて「会社の自分史」(=社史)になることができるのです。
「経営史」の意味は「メッセージ」
では、自社の「経営史」の「意味」はいったい何なのでしょうか。それは、一言で言えば「過去から今へ、そして今から未来へのメッセージ」ということになります。
歴史には「過去の歴史」と「現在進行中の歴史」があります。過去の歴史からはメッセージを受け取り、現在進行中の歴史は未来へのメッセージとして送るのです。「メッセージ」は端的に言えば「試行錯誤からの教訓」と「人間としての思い」です。過去の成功や失敗から得られた教訓とそれに取り組んだ先人の思いをメッセージとして受け取り、現在進行中の取り組みとそれに懸けている現在の思いを未来にメッセージとして送るのが社史なのです。そのことを念頭に置いて進めれば、社史づくりは成功します。
「経営史」をつくるのは「経営者意識」
それでは、「社史は経営史で、それを会社の自分史としたときの自分は経営者」だから、一般社員(従業員)は「社史=会社の自分史」の「自分」になれないのかといえば、ここが肝心なところです。「社史は経営史」と定義するときの「経営」者とは、「経営者」と、「経営方針を経営結果に結びつける社員」と考えなければなりません。経営とは「経営方針」と「結果」だからです。上記の説明でいえば「経営状況がどのように推移したか」の部分の主役は社員だということです。会社全体の経営をするのはもちろん「役員」と呼ばれる通常の意味での「経営者」ですが、部署部署ではそこを任された人がその仕事の結果を成功に至らしめるためになんとかしようと(management)します。これで「経営」が実現し、「経営史」が成立するのです。
これをさらに噛み砕いて言いますと、「経営史」という言葉は単に「経営者の経営ぶりの歴史」を意味するものではありません。極端なことを言えば、経営者がある経営方針を打ち出したのに対して従業員が反発して従わなかったという事実があった場合、それを記したものも「経営史」の中に含まれるという意味での「経営史」——ということです。会社の経営にまつわることを総合した「経営史」が「社史」となるのです。つまりは、従業員が一方の主人公として扱われていないものは十全な社史、健全な社史とはいえないわけです。これは社史(経営史)の大前提として制作の全過程で念頭に置かれていなければなりません。
「いい会社ほどいい社史ができる」理論——ホモ・ルーデンス理論とのかかわりも
もちろん、一般社員(従業員)は労働者ですから、だれでもいつでもこのような「経営者意識」を持つわけではありません。しかし、人間は「自己実現」を求める心を持っているので、仕事を通じてそれを満たすための創意工夫や努力をしようとします。これは人間の「本能」(比喩ではなく実際に)なので、社員は経営者の指示で動かされるだけでなく、むしろ自分で動くところにこそ力を発揮します。従業員がその機会を多く与えられる会社ほど、「経営史としての社史」は充実した豊かものになり得るのです。これを私たちは「『いい会社ほどいい社史ができる』理論」と呼んでいます。経営の三大資源は「ヒト・モノ・カネ」と言われますが、「ヒト」は自ら思考も行動もしない「モノ」「カネ」とは異なります。「企業は人なり」なのです。
さらに、ホイジンガという人が提唱した「ホモ・ルーデンス」という理論があります。「ホモ・ルーデンス」とは「遊ぶ人」という意味で、文化は人特有の「遊び」で発展するというものです。この考え方を突き詰めると、一般に「仕事」は決して「面白い」ものではないように思われがちですが、実はゲームとしての本源的な面白さがあると解釈することが可能になります。
仕事がゲームとして面白いのは経営者だけだろうと言われるかもしれませんが、ホイジンガの説を逆からみれば、およそ人間特有の文化的活動(労働の内容は基本的に人間の文化です)はすべてゲーム性を持つのです。上記したようなmanagementはゲームそのものということになります。このゲーム性、面白さを社員が自覚できる会社こそあるべき会社であって、その社史も「会社を強くする」良い作品になると思われます。
とにかく「いきさつ」を記す
さて、「経営史」と言えば何か難しい高尚なもののようですが、要はその時どきの経営が行われた経緯や個々の経営事象の「いきさつ」を記すということです。これらの動きの経緯が具体的であればあるほど、関係者なら身を乗り出して読むことでしょう。もちろん、企業秘密をはじめ伏せることが正当な判断である場合もあり、何でもかでも書けばいいということではありませんが、基本は間違いなく「積極的にありのままを書く」ということです。資金繰りの苦労や、さまざまな失敗談、係争事案などは積極的に書かれない傾向がありますが、ここというところでそういうこともしっかり書いてこそ本物の社史になるというものです。少なくとも、良い社史にするために必要ならば、ギリギリまでは書くということでなければなりません。近年、いわゆる「徴用工」の問題が耳目を集めていますが、強制的に連行された朝鮮の人々を過酷な労働に従事させた事実を勇気をもって自らの社史に記した会社もあれば、このことには社史でまったく触れていない会社もあります。また、いわゆる「徴用工」ですらない、当時の交戦相手国から強制連行された人々を、敗戦直前の極限的にまで切迫した異常な環境下で非人道的に酷使して多数を死に至らしめてしまった会社もありますが、その社史にはこの大事件についての記述がなかったため、「社史に書く」よう相手側から要求されているというような問題もあります。少なくとも「良い」社史を作ろうとするなら、国際問題にまでなった公然の事実を記述しないという選択肢はあり得ません。
考えてみてください。私たちが日本史でも世界史でも技術史でも文化史でもおよそ「歴史書」というものを読むときに「知りたい」と思っているのは、その対象が今日に至るまでの「実際のいきさつ」ではありませんか? そしてなぜ「いきさつ」を知りたいかということを突き詰めて考えてみると、それはその「いきさつ」を「ヒント」として普遍化し、自らの生き方や考え方、行動のあり方をより正しく良いものへと高めるための糧にできないかと考えるからではありませんか? 現在あるものの歴史的経緯を知りたいという興味、関心は、そのようにより正しい「解」を得ようとして模索する、人間の本源的な「知的欲求」なのです。「経営史(会社経営の歴史的経緯)を書く」ということは、関係者を含む読者のそうした人間的な知的欲求に積極的に応える作業であり、社史の価値は、結局、その成否で決まります。
必ず「背景史」を
一企業の経営史といえども、立派な「歴史書」です。社史(company history)はcomhistory(コムヒストリー)と書き表されることもあり、そこには自ずとコミュニティーの歴史というイメージが字義に含まれてきます。一つのコミュニティーの歴史は世界史など大きな「歴史」を成り立たせる部分であると同時に、大きな歴史の中に成り立っている部分でもあります。その意味で、社史もリアルタイムの背景を含む背景史と切り離しては成り立たないものです。上記の「いきさつ」を語る社史は、当時の世相、政治・経済・文化の背景、技術環境などを有形無形に反映したものになります。その会社のことばかり書くという視線ではその会社のことは書けないのです。社史編纂は「歴史書」を書くという大きな仕事をする意識のもとに取り組むべき作業です。
さまざまな時代背景とともにある社史の流れ(「写真で見る社史年表」サンプル)
時代々々の「課題」を意識して書く
会社というものは、必ずその時代々々の「課題」を持っています。創業時には仕事を継続可能な事業として成り立たせることが一番の課題ですし、そうやって経営基盤が出来たら、規模や事業内容の拡大・発展という課題が出てきます。そうした目標的課題は別にしても、ただ存続するだけでも課題が必ず出てきます。競争社会であることと、時代の流れという二つの基本条件の下に、経営環境が変化するからです。発展よりも、むしろ「存続」が問題であって、存続のための課題をどう乗り越えたか、あるいは正面から乗り越えられない場合はどう回避しどう解決したか、というようなことが必ずあって、会社は現在に至っており、それこそが発展であると言ってよいのかもしれません。存続を第一義としながら、結果的に発展していく、進化論的でもあり弁証法的でもあるのが会社の生の歴史です。ですから、どこかに生々しいものを感じさせることこそ「本物の社史」の証明と言えるかもしれません。
面白い社史の神髄は「苦労話」
社史は必ず「面白いもの」にできる——
これが弊社の基本的な信念です。そう考えるポイントはとりあえず下記の2点です。
1.事実の「面白さ」の意味を誤解しないこと
社史に書かれることは、すべて現実に起こった出来事です。「事実は小説よりも奇なり」といいますが、「奇」ではなくても、「現実」というものは「作り話ではない」というところに重みと説得力があるため、それだけで文章としてはっきりした強みがあるのです。
それでも社史は一般に「面白くないもの」「読む気がしないもの」の代表のように言われているのですが、それは読む側の興味が初めから薄いから、いくら良い社史でも「面白くない」ということであって、それをもって社史の価値とすることはできません。
社史というものは、その会社や業界、その産業に関心を持つ人に対して「価値あるもの」(平たく言えば「面白いもの」)であればよいのです。
ですから、始めから関心がある人の期待に応えることが求められるのであり、そのことを意識しての編集制作が必須の前提であることを考え方の土台から外してはなりません。
2.「苦労話」とは
「苦労話」には、大まかに言えば2種類があります。「存続のための苦労話」と「発展のための苦労話」です。これは便宜的な分け方で、実際には発展がなければ存続できないのが企業の宿命ですから、すべては発展のための苦労としてもいいのですが、とくに発展を求めない、現状のままでいたいという企業にも現状のままを許さないのが資本主義社会ですから、心情的には「存続のための苦労話」という言い方の方がしっくりくるケースも少なくありません。
と言いますか、実は、逆に、「発展のための苦労話」というのは貴重ではあるが少数なのであって、「苦労話」というのはほとんどが「存続のための苦労話」と考えて作るところにこそ、社史の「面白さ」が出てくるように思われます。「存続のためにこそ苦労して発展を目指していく」というところに「社史の面白さ」——ドラマ性があります。これが「苦労話」なのです。そうした事実の中のドラマ性こそ「真実」であって、上記1の「関心がある人」だけが味わえる「面白さ」なのです。
社史の目的?
インターネット上には「社史の目的」についていろいろなページでいろいろなことが書かれています。その多くは、「社史を制作する目的にはいくつかがある(関係者への謝恩、社員教育に利用、会社PRに、社員啓発に、etc. )、その中でどの目的に重点を置くかを決めておかないと作業方針にブレが生じて困ることになる、だから最初に制作目的をはっきりさせておかなければならない、と説いているもののようです。
しかし、これらのことが「社史を作る目的」と聞いて、心から「なるほど!」と思える人がどれほどいるでしょうか。冒頭で述べた経営者の方々の「残したいから」「伝えたいから」という思いとどれほど直結しているでしょうか。そうした実用的な「目的」を掲げるくらいなら、私どもはこう言ったほうがよほど「ピンとくる」のではないかと思います。
「社史を作る目的は自分たちがやってきたことが後世に忘れ去られないため」
「私たちの築いた、あるいは現在築いている歴史が後世において誤解されたり、歪められたりしないため」
こういう言い方のほうが、とりあえずは率直な「目的」として実感されるのではないでしょうか。
そのことが、社史の普遍的で本質的な「目的」である「会社を強くする」という結果につながっていく、というのが、正しい順番ではないかと思います。
社史(経営史)というものの本質的な側面を考えるなら、「弊社の制作理念」の社史の本質的な側面についてをご参照いただければ幸いです。
そういう「実用的な価値」は会社が社史を作る労力や費用の対効果として検討されて然るべきですが(本稿でも後述します)、それらは社史本来の「目的」とは厳しく峻別されなければ、肝心の歴史の歪曲を許すことにもつながりかねません。「価値ある社史」を残すために心すべきことです。
また、最近は「企業アーカイブ」という言葉が流行っていますが、良い社史は決して単なる企業アーカイブではなく、そうした読者の「人間的な」知的欲求に「人間として」応えようとするクリエイティブな作品でなければなりません。
「記念誌と社史の違い」?とは
「記念誌と社史はどう違うのか」というのもお客様からよく頂くご質問です。社史に限らず、「年史」と呼ばれるもの一般についての疑問のようです。「記念誌」と「社史」は全く別の意味の言葉ですから、本来はあり得ない疑問なのですが、「記念誌」として社史や団体年史が作られるケースが多いため、整理して理解したいということと思います。
「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日
という俵万智さんの有名な歌がありますが、そのように「記念」というのはある出来事を特別なこととして忘れないために心に刻むことです。例えば会社その他の各種法人(学校法人、医療法人、社団法人、社会福祉法人など)や団体が創立○○周年を迎えたという場合などに、その活動を長年にわたって続けてきたことの意義を認識し、喜びや感慨を込めて心に刻み記憶するツールとするのが「記念誌」ですから、その中に社史や年史という歴史記述がなくても記念誌として成り立ちます。祝辞や回想録、懐かしい写真、関係者インタビューや思い出を語る座談会などでまとめることもできますから、その場合には「記念誌」と「社史(年史)」の混同は起こりません。
しかし、この「記念誌」の中に体系立てられた歴史記述があれば、「社史(年史)入りの記念誌」ということになりますし、多くの社史がそういうことで作られるということになれば、「社史と記念誌はどう違う」という疑問も出てくることになります。極端に言えば、祝辞やインタビューや座談会がない純然たる「社史」であっても、それが「記念誌」として作られれば、「記念誌でもあり社史でもある」ことになるわけです。
「記念誌と社史はどう違う」へのお答えはそれだけのことですが、では「記念誌+社史(年史)」はどう作るかということになると、記念誌的要素をどのように取り入れるかの創意工夫が必要になります。しかし、この場合にも「社史は経営史」の原則は崩せません。「記念誌」であることに気を取られて本質を忘れると社史は社史でなくなります。

そのことを踏まえた上での記念誌的社史(「記念誌+社史」)の作り方については、別項「記念誌・社史の制作手順」(準備〜その1〜その6)を参考にしていただければ幸いです。これは社史だけでなく年史一般を含む記念誌づくりにも役立てていただけるものと思います。
その中でも触れていることですが、記念誌、特に年史記述が主体でない純然たる記念誌を制作するにあたって留意すべきことは、平凡な定番メニューと思われがちな「挨拶」とか「祝辞」とか「回想談」などの「寄稿」を、内容の深い、熱のこもった感動的なものにするべく最大限の努力をすることです。実は、これらの「寄稿」は、「記念誌の命」と言ってよいほど大切なアイテムなのです。これについては「(4)寄稿者の人選と寄稿依頼」で言及していますのでご参照ください。
★これからの「新しい社史」とは?——「全員経営」の視点で
「社史110番」の「新しい社史って?」の項でも触れていることですが、時代の流れの中で「社史」も変わっていきます。装丁デザインや誌面レイアウトのスタイルももちろんそうですが、もっと本質的な「内容」も変化していきます。
以下、「新しい社史って?」から再掲します。
…………………………………………………………
「経営史」と言えば、「経営者」が主役のように思われることでしょうし、実際にあえて意識もされずそういう考えで多くの社史が作られてきています。経営者がいて、労働者がいて、経営者の指示の下、労働者は賃金をもらう見返りに働かされる——これが「会社」だというのが長い間の常識だったし、今でも相当程度にそれは通用している常識なのですが、その常識だけでは「社会の変化」に合わせていくのが難しくなってきています。社員が単なる「働かされる労働者」だという常識はだんだん通用しなくなってきているのです。
現代の、またこれからの企業は、経営者が会社の「舵取り」をするだけでは所期の経営結果が出ず、社員の、現場での、スキル的なものも含めた「経営判断」を得て好結果が実現できる場面が増えてきます。これからの社史=経営史の主役は経営者と社員であり、時には(というより、しばしば)立場が逆転することもあり得ると思われます。ある種の「社員持株制度」や「執行役員制度」などは、その予兆を含むものではないでしょうか。
というよりも、むしろ、経営というものは経営者一人の判断や指示だけで成り立たないのが当たり前で、昔からそれが「本質」だったのですが、少ない「情報」で経営ができた時代にはそれが目立たなかっただけなのです。全員で情報を最大限に持たなければならない高度な競争社会になればなるほど、「全員経営」が求められてくるのです。
このように、これからの「新しい社史(経営史)」は、「全員経営」の経営史に変貌していくものと牧歌舎は考えています。
…………………………………………………………
後述する<制作メモ4>「近近社史」のススメもこの考え方に基づくものですのでご一読ください。
経営史=会社の自分史の書き方の基本——社史の主語は一人称の「当社は」 (牧歌舎方式2—「当社は」を主語として書く)
正しい歴史記述のためには「客観性」が当然求められますが、そこにとどまっているだけのものは「社史」ではありません。客観性を備えた内容が、企業としての主観の下に記述され、表現されるということでなければなりません。自分の人生について客観的な事実を並べただけでは「自分史」にならないのと同様です。「社史が会社を強くする」ための大前提は「会社を人間として書く」ことなのです。自分史の文章の主語が「私は」であるように、社史の主語は一人称の「当社は」でなくてはなりません。社史は「当社は」を主語にして自分史のように書くのがコツなのです。
これだけではよく分からないかもしれませんが、要は、
「○○株式会社(自社のこと)は○○年に本社を○○に移転した」
と書くのではなく、
「当社は、○○年に本社を○○に移転した」
と書くということです(創業期などの記述は別)。あるいは、
「当社の○○工場が○○年に建設された」
でなく、
「当社は○○年に○○工場を建設した」
と書くということです。
詳しくは「弊社の制作理念」の社史の文章の主語、社史の文章の本当の主語をご覧ください。
「社史の主語は『当社は』」と言えば、経営者(経営陣)が主人公で社員は脇役のように思われるかもしれませんが、先にも書きましたようにそれは全く違います。主語としての「当社は」は形式上、経営陣ということになりますが、「社史は経営史」というときの「経営」者は、「経営者感覚」をもって活動する社員すべてとしてこそ、本当の「経営史」が実現します。優れた歴史書はその中に置かれた人々の歴史を動かす姿や思いまでもを彷彿させて読者の知的欲求を存分に満たします。優れた経営史もそのようにして社史本来の目的を果たすのです。書き方としては、主語は「当社は」で一貫させ、個々の社員(経営者も含む)の現実的活動を記述する場合は「当社」による紹介という気持ちで語るようにするのがコツです。
社史は基本的に文書(ドキュメント)であることを確認しておきましょう。 (牧歌舎方式3—文が本体、写真は資料)
最近の社史はA4判などの大型本が多くなり、記述のあちこちにカラー写真が多数配置される傾向にあります。その傾向が高じて、写真が主役のような編集コンセプトのものが増えています。つまり、「文としての社史」は、現象的には後退してきているのです。
写真の多用は昨今の、特に若者の「文字離れ」に対応したものと言われ、「読ませる工夫」と説明されることも多いのですが、写真に過度に依存することは禁物です。文としての記述内容を補うものに限定されるべきなのです。きれいなカラー写真をたくさん使ったからといって「読ませる工夫」にはなりません。むしろ肝心の「文」を読ませないという逆効果さえ生じます。読ませるために写真を使うなら、少数、できれば1枚の写真で記述内容を補い、読みたくなる効果のあるものを使うべきです。
●1枚の写真で「文」を読ませる

洋の東西を問わず、写真や挿絵入りの歴史書は多数出版されていますが、特殊なものを除いて、歴史書の本質は「文」にこそあります。「人が人に言葉で伝える」のが歴史書であり、写真や挿絵はそこに添えられる「資料」なのです。当たり前のことですが、昔の本を読む私たちにとっても、今作る本を将来読む人にとっても、「どのように文で書かれたか」が眼目なのです。手っ取り早く見られる画像や映像が表現手段として前面に出てくる中で、言葉が後方に押しやられると、歴史というものは書き残せなくなっていきます。「文が本体、写真は資料」は当然の前提なのですが、つい踏み外しやすい原則ですのでしっかりと心しておかねばなりません。
牧歌舎のモットーは、冒頭に掲げたように、
「読まれない社史」よサヨウナラ。
社史は必ず「面白いもの」にすることができます。
というものです。絵や写真で「読ませる工夫」などと言うのは、社史がもともとつまらないものであると認めたようなものです。つまらないものをなんとか読ませようと姑息なことを考えるのでなく、読者から真に知的な興味や関心を持って「読まれる」条件を確認してください。
ページレイアウト上の飾り同様、製本上のデザインに凝り「すぎる」のも考え物です。将来において社史が参考にされるのはその記述内容であって外見ではありません。
牧歌舎は、社史ライターを社長とする会社として記述文の品質にこだわり、「熟読される社史」を目指しています(牧歌舎社長の社史・記念誌執筆作品)。
エディトリアルデザイン>グラフィックデザインで
社史の誌面レイアウトの基本はエディトリアルデザインとグラフィックデザインですが、最近はグラフィック化の傾向が進んでいます。グラフィック化とは、中身の文字や写真について、ファッション誌や広告印刷物などに見られるように視覚的な魅力を持たせるもので、見出し文字に画像化したデザイン文字を使ったり、罫線などの定番要素にオリジナルな装飾的描画を用いたりすることで美術的効果を高めます。昔の質実な社史と違って、最近はそれを付加価値として多用する傾向にあります。
このグラフィックデザインに対応するのがエディトリアルデザインで、これは本(書籍)の文字組の読みやすさ(可読性—readability)を求めて本作り職人たちが経験を元に築き上げてきたセオリーに基づいています。社史は書籍ですので「エディトリアルデザイン>グラフィックデザイン」のバランスを保たねばなりませんが、これが無頓着に逆転されているケースも見受けられます。過剰なグラフィック化はハイコスト化にもつながることなので、当社は伝統的なエディトリアルデザインのセオリーを重視しながら、現代的な「感性品質」のニーズに添うグラフィックデザインを取り入れ、「読みやすく、美しい」誌面で構成するリーズナブル社史を目指しています。
牧歌舎の「記念誌的社史」
上記したように、牧歌舎の基本的な考え方はあくまでも文字中心の「熟読型社史」ですが、昨今はお客様からグラフィックな作品を求められることも多いため、先にも「記念誌とは」で述べた「記念誌+社史」となる作品を「記念誌的社史」と呼んでグラフィックな要素も取り入れた作品をお作りしています。考え方はあくまでも「エディトリアルデザイン>グラフィックデザイン」を貫き、過剰なグラフィック化を抑えたリーズナブル社史として、視覚的な「感性品質」を適度に加えた作品として好評をいただいております。そのレイアウトサンプルのいくつかを以下にご紹介します。
●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「巻頭挨拶」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「トップ対談」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「祝辞」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「通史」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「コラム」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「テーマ編」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「OBOG古参社員座談会」

●記念誌的社史レイアウト制作サンプル「若手中堅社員座談会」

「内部向け」>「外部向け」であること (牧歌舎方式4—内部が先、外部は後)
社史の基本的な組立は、「口絵」に始まり、経営トップの「挨拶文」、取引先などからの「祝辞」と続き、メインの部分である「通史」、座談会などの「企画ページ」と展開したのち(「企画ページ」が「通史」より前に来る場合もあります)、業績推移グラフや組織の変遷図などの「資料編」および「年表」で締めくくり、最後は「編集後記」「奥付」で終わる形になります。
こうした基本形を一応認識した上で、制作開始にあたって「企画」を行うわけですが、ここでまず最初に考えておかなければならないことは「社内向け」という感覚を「社外向け」より優先させるということです。「両方とも同等に」という選択肢も考えることはできますが、実際にはうまくいきにくいものです。「内向き」か「外向き」かの度合いで、原稿内容や編集の仕方、全体構成、製本形式や装丁デザインの方向性も決まりますので、よく確かめておく必要があります。作業の方向をブレさせないという話題が上記にありましたが、実際にはここがブレを防ぐ最も基本的な分岐点であって他はその後の派生的なものにすぎません。(「内部向け」「外部向け」を必ず第一番に考えるこの「牧歌舎方式4」は基本コンセプト確認の方法として現在広く普及・定着してきています)
- 弊社の制作理念 >「牧歌舎方式4」の意味 をご参照ください。
肝心なことは、「社内向け」の社史、少なくとも「どちらかと言えば社内向け」の社史こそ、良い社史になるということです。○○周年で社史をつくるとなれば、自ずと記念誌的色彩を帯び外部の人に見てもらうことも考えた内容になることでしょう。それはけっこうなことで意義もあることですが、そうであってもなお、「「内部向け」>「外部向け」」は社史が社史であるための最低限の条件です。
「社史手づくりサポート」サービス
上記のように、内部向けを意識することで良い社史になることをさらに追求していけば、内部で「手づくり」できれば、それこそ「理想的な社史」になるのではないかということが考えられます。
そこで、弊社は、2019年より「社史手づくりサポート」サービスを開始しました。
社史の手づくりは、概ね下記のように進行します。
(1)企画の検討と決定
(2)スケジュール決定
(3)資料準備
(4)写真・図版準備
(5)素年表作成
(6)原稿作成作業
(7)記念企画の実施(座談会・対談など)
(8)掲載写真選択
(9)レイアウト
(10)原稿確認・校閲
(11)原稿整理
(12)DTP(組版)
(13)校正
(14)装丁デザイン
(15)印刷製本
(16)検品・完成
これらの各ステップを、社史編纂委員会など会社の内部スタッフの方々に実行していただくわけですが、それぞれのステップについての必要な説明、アドバイス、また求められれば技術的なサポートやノウハウ、情報は弊社より提供します。
特に、「原稿を自分たちで書く」という点が最大のポイントで、社員の方やOB・OGの方などに手分けして原稿を書いていただき、弊社は必要なアドバイスと最終的な補整のみを行いますので、プロのライターを起用する場合の多額の原稿執筆料や書き直し料を省くことができるばかりでなく、それ以上に、真に「自分たちで作った」実感に満ちた社史が実現します。
最近、この方式で社史を制作された会社様から下記のような内容のお便りを頂きました。
「自分たちで社史ができるかどうか不安だった頃、牧歌舎の社長にお越しいただき、
・プロのライターが皆さんから話を聞いて原稿を書けば、それなりのものにはなるが、現場の人が書いたものとはやっぱり迫力が違う。
・いろいろな人が原稿を書けば、みんな違う文体になるのは当たり前。わざわざ無理して合わせることはない。
・コンクールに出すわけではないので優劣があるわけではない。
・社史は出来たものも大事だが、出来る過程も大切。
・なんとかなりますよ。
——と言われ、我々でもできるかもしれない、と思いました。そのころ、もう一社にも話を聞いていましたが、そこは、こちらで原稿を書くにしても、プロのライターの書き直しが最低必要、写真もプロの写真家に撮らせる——などなどの話で、さぞかし立派なものができるだろうと思いました。費用の面もありますが、我々が選んだのは「社史は牧歌舎と一緒に作る」でした。
その後は、何もわからない我々を先導してもらい、時には、無理を言ったりしたこともあったかと思いますが、一緒に作っていただいて感謝します。完成できたのは牧歌舎の皆さんのおかげです。本当にありがとうございました」
ぜひ、この「社史手づくりサポート」サービスに挑戦していただきたく思います。
「社史」とは社会貢献史——が本道 (牧歌舎方式5—社業への誇りを土台に)
企業活動の直接的目的は利潤の追求ですが、その利潤とは生産物を介しての社会とのギブアンドテイクの結果と考えるのが市場原理に即した考え方です。それを今一歩踏み出して、社会へのギブというのはビジネスを通じた「社会貢献」であると堂々と言えてこそ、社史は「理念」をもったものになります。そうであってこそ、上記の「価値」もくっきりとしたものになるのです。
これはいかにも当然のことのようですが、なんと言っても企業の直接的目的は利潤の追求ですので、「社会の役に立つ」「社会の役に立ちたい」「社会の役に立ってきた」ということに強い思いを込めなければ記述内容はリアリティーを失ってしまいます。
自信を持って、社史を自社の「社会貢献史」として書くことこそ、社史づくりの本道です。これは自社への強い愛情と誇りに裏打ちされて初めて実現できることで、漫然と歴史を追うだけでは不可能です。社史づくりを始めるにあたって、まず押さえておいていただきたい第一のキーポイントです。
「自分の仕事への誇り」——これこそ、人が堂々と社会に生きるための最も根源的な強い精神の支柱であり、自信、意欲、勇気、ひいては他者への尊敬、愛情など、肯定的な価値観の源泉でもあります。個人にとっても会社にとっても、社会への貢献という事実認識を通してもたらされる「自分の仕事への誇り」は、まさに社会の中で生きていくための原動力なのです。社史を作るにあたっては、常にこのことを念頭に置いておきたいものです。
- 弊社の制作理念 >「社史とは社会貢献史」……の条件 をご参照ください。
このホームページでは随所に「会社を強くする」社史という言葉を使っています。それはどういうものか、ここまで読んできていただいた方にはだいたいのイメージはお分かりいただけたと思いますが、この第5原則こそ、その最終的集約です。昔から人間社会というものは「公」と「民」に分けて論じられるのですが、実際には人間は「公」と「民」に分かれて生まれてくるのではなく、すべての人は「民」なのです。「公」は混乱を防ぐための必要から生み出されたシステムにすぎず、そこに万民の幸福が仮託されているとするのはよく出来た幻想です。本当の「All for One, One for All 」は個々のOneが創り出すものであって、OneがなければAllはないと考えなければなりません。OneがAllを担ってこそ「All for One, One for All 」なのです。その原点を踏まえている企業こそ原理的に最強なのです。ここまでお読みくださった方にのみ、「会社を強くする」社史とは何かの結論を申し上げました。
まとめ
さて、ここで「社史制作の5原則」をまとめておきます。各タイトル右側の「↑」クリックでジャンプします。その後は各ブラウザの「←」(戻る)ボタンクリックでこの画面に戻れます。
以下は社史制作に当たっての注意点をメモの形で列挙したものです。
<社史制作メモ>
<制作メモ1>社史は企業の「命の記録」—「魂の社史」を!

社史について、「大きな会社がただ『箔付け』のためにつくるものだ」とか、「その歴史を都合良く記述するものだ」とかいう批判的な角度からの見方は昔からあります。国の歴史書ですら為政者の意向で事実を脚色したり隠蔽したりしてつくられているというのが定説ですし、歴史書はそれをつくる人の立場で記述されるものであることは認めないわけにいきません。
けれども、そういうことをもふまえた上で、社史の本質は企業の「やむにやまれぬ命の記録」であり、「言葉にならない意思」を最大の動機として書き残される経営史なのであって、きわめて「人間的な意味の深い」制作物であると当社は考えています。
その動機は、大企業に劣らず中小企業にも当然あるものです。大企業には大企業の、中小企業には中小企業の「やむにやまれぬ命の記録」が書き残されるべきと当社は考えます。
人はなぜ「書き残す」のか——これは考えていけばいくほど興味深い哲学的なテーマであり、また「言葉を持った生物の生理」という科学的なテーマでもあり得ます。答を出すより考え続けることに価値のある問題であるといえるかもしれません。
私どもは、こうした基本認識に立って、企業様の求められるものをより深く理解し、より深く表現できるようにと努めながら、社史づくりのお手伝いという仕事に日々取り組んでおります。
<制作メモ2>社史の「実用的価値」
社史づくりに取り組むときには、上記しましたように、まずその「本質的な目的」をはっきりと自覚しておきたいものです。
……その上で、社史の価値・効用について実用的な角度からもう少し具体的に明文化したかたちでまとめてみますと、大略次のようになります。
1.未来への道しるべとして
温故知新……「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」と読まれるこの言葉の真意は「過去の事実を再研究して新しい方法を発明する」ということです。社史づくりは会社の歴史を噛みしめながら明日への新たな道標をうち立てる営みです。
2.社員教育の資として
社員、特に若い社員にとって、自社の歴史への深い理解は仕事への意欲と誇りの源泉となります。何よりも、自社の成り立ちについての正確な知識こそ、真の愛社精神を生む土壌です。その意味で社史は絶好の社員教育のよりどころといえます。
3.歴史を築いた先人や取引先への謝恩に
創業期から社業発展につくしてきた先人の労苦をしのび、また、長く貴重なパートナーシップを保ってきた取引先や関係者の人々に謝意を表すため、社史はこの上ない記念品となります。
4.好機ををとらえた強力なPR材に
「創業○○周年」「会社設立○○周年」「創業者生誕○○周年」などの「節目」は、自社を改めて各方面に広くPRすべき絶好の機会です。このチャンスを生かすためにも、社史は最も効果的なツールとなります。
他にも、「業界史、ひいては日本産業史としての意味がある」「経営上のヒントが得られる」「実際の業務に資料として活用できる」などのメリットも挙げられます。このように、会社の歴史を「本として残す」ことには測り知れない深い意義があるのです。
このほか、上記のような本筋の「実用的価値」とは別に、「社史のビジネス戦略的効果」も現実には無視できないものです。これについては、
- 弊社の制作理念 > 社史の「ビジネス戦略的効果」について をご参照ください。
<制作メモ3>>社史の歴史と最近の傾向
明治中期に日本が産業近代化の道を歩みはじめてから1世紀以上になりますが、太平洋戦争以前は社歴の長い企業の絶対数が少なかったことなどから社史が発刊されることはあまり多くありませんでした。戦後の復興期を経て、高度成長期に入った昭和30年代からは戦前創業の会社が社史を刊行するケースが増えはじめ、昭和50年代以降は、戦後創業会社がこれに加わって、社史の発刊数は飛躍的に伸びました。さらにオフセット印刷の普及や電算写植の発達、最近ではDTPの進展で、社史の制作は企業規模の大小を問わず、周年事業の代表的なものになってきています。
以前は社史といえばいかめしいイメージで、箱入りの豪華本というのがほとんどでした。これは企業の堅実さや伝統の重みをアピールすることが重要視されたからです。今でもそのスタイルが主流ですが、時代の移り変わりとともに新しいコンセプトにもとづく作品も数多く現れてきています。
いわゆる重厚長大型から軽薄短小型への産業構造の転換後は、上記の「牧歌舎方式3」でも述べたように、一般的な活字離れの傾向も手伝って、文字よりも写真などの図版を多く取り入れる傾向が現れました。何百ページというものは減り、数十ページ—100ページ台のものが多くなっています。また、その反面、製本は親しみやすい並製本にしながらも、やはり文字中心で「熟読される」ことを求める企業もあり、この場合はA4判やB5判などの大型本ばかりでなく、携行しやすいA5判や四六判の単行本タイプも採用されています。
<制作メモ4>「近近社史」のススメ—「近過去・近未来型」社史を推奨中
最近、たとえば10年前に「50年史」として社史を作っており、そこから10年後を迎えるにあたり「60年史」を作りたいのだが、こういう場合どういう考え方で内容を企画すればよいか、というご相談を受けることが多くなりました。
こうしたケースでは、当社は対象期間を思い切って「近10年」に絞り、その間の「経営」を丹念にたどって検証する「近10年史」を強くお薦めしています。タイトルを「60年史」とするにしても、50年史の部分は概略のダイジェストあるいは年表のみにとどめ、事実上は最近の10年間を克明に振り返る社史とすることが最善と考えるからです。
その理由は、いわゆる「創業以来の歴史を振り返る」という作業は10年前の「50年史」で達成されており、それに比べれば「この10年」は、歴史は浅いけれども「これからの10年」への直結性が高く、真剣に検証することで近未来へ向かうための会社の血肉に出来る可能性が高いと考えられるからです。
最近も、10年前に「70年史」を作っておられたある会社様の「80年史」を制作させていただきましたが、70年史部分は巻末年表に含めたのみで、実質的には完全な「近10年史」とし、それでもページ数は「70年史」の220ページを上回る240ページとなりました。その10年間の組織改革や技術革新の取り組みとその結果を詳細にかつシビアに見直し、そのまま進むべき点、考え直す点、新たに出てきた発想や予測される課題への対応策などを取り込むために、それだけの紙数が必要だったからです。こうして出来た「80年史」は、その充実度で非常な高評価を頂きました。
この企画で不可欠ともいえるほど重要な役割を果たすのが「近未来を語る座談会」で、紙上の歴史でなく自身で知っている近過去をどのように再評価して近未来に生かすかを社員同士で真剣に語り合う企画となります。
記憶もあり資料も豊富にある「近過去」を「近未来」に生かさない手はありませんし、またこの「近近社史」は、10年後の「近近社史」につながっていきます。
「社史は経営史」の考え方は、これによってより身近で現実的なコンセプトとして広く認識されていくものと考えています。
<制作メモ5>優れた社史は「文学」にも
経営史として「企業の自分史」となっている社史は、「文学作品」としての価値を持ち得るものです。
「社史は文学である」と言えば、「それは違う。社史はあくまでも事実の記録であるべきで、文学などであってはならない」という反対意見があるかもしれません。しかし、『古事記』『日本書紀』をはじめ『大鏡』『増鏡』、『太平記』『吾妻鏡』などの歴史書が日本文学の一ジャンルとして確立されており、諸外国においても多くの歴史書が同様に扱われている事実からも、優れた歴史書の文学性は明らかです。社史が「読んでも面白くないもの」と思われているのは、実はそれが単なる「会社の歴史—客観的記録」であって「経営の歴史—会社の自分史」になっていないからです。「会社の自分史」になっていれば、誇張や脚色のない淡々とした記述であっても、読み手は興味を覚え、ぐいぐいと引き込まれ、感動します。そのような社史づくりを目指してください。
社史って面白い!
牧歌舎マスコット「おすず」くんお薦めの参照リンク
社史について調べる(国立国会図書館サーチ リサーチ・ナビ)
渋沢社史データベース)



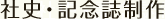



.jpg)





































